先週後半にアキバで Core 2 Duo E8400 の流通が一時的に回復したらしい、というニュースを見つけ、それならということで買ってきました。
品薄「Core 2 Duo E8400」の流通量が一時回復!? 購入のチャンスか! (ASCII.jp)
45nm CPU の本格的な供給再開はボーナス時期の見込み、ということなので、今回のはおそらく本当に一時的なものなのだと思います。Yorkfield も発売されて、45nm CPU に対する人気がバラけたのも一因かもしれませんが、現時点でクアッドコアにそれほど魅力を感じていない私にはちょうど良かったです。本当はもうボーナスまで待つつもりになっていたんですが、つい(ぉ。
今までも Pentium Dual-Core を 2.66GHz にオーバークロックして使っていたので、ほんの 12% アップにすぎない E8400 でどの程度パフォーマンスが向上しているのか、試してみました。
ベンチマークは CrystalMark 2004R3。微妙にバージョンアップしていますが、データには互換性があるらしいので、2004R2 で取った E2140@2.66GHz のデータも載せておきます。
| CPU | Pentium DC E2140 @2.66GHz(333MHz×8) |
Core 2 Duo E8400 @3.00GHz(333MHz×9) |
|---|---|---|
| Mark | 121278 | 136921 |
| ALU | 23447 | 29664 |
| FPU | 28396 | 31535 |
| MEM | 14269 | 15879 |
| HDD | 8681 | 8568 |
| GDI | 14851 | 16447 |
| D2D | 4915 | 4906 |
| OGL | 26719 | 29892 |
L2 キャッシュ効果ですかね?整数演算値がクロック比以上に伸びてます。これは体感速度にもけっこう影響するかも。まあ、いずれにしても今のシステムじゃディスク I/O とネットワークアクセスがボトルネックになって、通常使用ではあまりパフォーマンスアップの恩恵を受けられないかもしれませんが、映像処理系はけっこう高速化するはず。
ということで、続いて 3D 系のベンチ結果を。
| クロック | Pentium DC E2140 @2.66GHz(333MHz×8) |
Core 2 Duo E8400 @3.00GHz(333MHz×9) |
|---|---|---|
| 3DMark05 | 7776 | 7886 |
| 3DMark06 | 4062 | 4139 |
| FFXIBench 3-L | 9978 (計り知れない) |
11053 (計り知れない) |
| FFXIBench 3-H | 7223 (計り知れない) |
8386 (計り知れない) |
3DMark 系はグラフィック性能への依存度が高く、リリース時期的に SSE4 にも対応していないので、あまり差が出ないですね。逆に CPU 依存度の高い FFXIBench は順当に上がってきてます。
とはいっても最近ゲームしなくなったので・・・より自分の用途に近い RAW 現像でベンチ。適当なベンチマークソフトが見あたらなかったので、実際のアプリで実測してみました。以下の 2 パターン。
- EOS 30D で撮った 50 枚の RAW 画像を DPP 3.2.0.4 で解像度 1800×1200、画質 8 の JPEG データにバッチ変換
- α700 で撮った 50 枚の RAW 画像を Image Data Lightbox SR 1.0.01.10010 で圧縮レベル 2 の JPEG データにバッチ変換
| クロック | Pentium DC E2140 @2.00GHz(333MHz×6) |
Pentium DC E2140 @2.66GHz(333MHz×8) |
Core 2 Duo E8400 @3.00GHz(333MHz×9) |
|---|---|---|---|
| DPP 3.2.0.4 | 239sec. | 181sec. | 150sec. |
| Image Data Lightbox SR | 292sec. | 239sec. | 199sec. |
まあこんなもん、といったところですかね。どちらもおそらく SSE4 にはまだ対応していないはずなので、単純に動作周波数+L2 キャッシュが効いているだけだと思います。でも 12.5% の周波数向上に対して処理速度が 17~18% 上がっているので、効果という意味では御の字かな。
Pentium DC を買ったのが冬場、今が春で外気温が全然違うため、どの程度発熱が抑えられているかは正直分からないのですが(換装直前の Pentium DC の動作温度を計るのを忘れてしまった)、少なくともオーバークロックした Pentium DC よりは消費電力も発熱も少ないはずなので、そういう意味でも効果はあったかと。ちなみに、リテール品付属のクーラーは Pentium DC 同様に銅コアのないシンプルなクーラーでしたが、ファン自体は同じでヒートシンクも形状は共通ながら、高さが Pentium DC 用の約半分に抑えられていました。このことからも、いかに Wolfdale の発熱が少ないかが分かると思います。
正直ここらまでくると PC 性能の向上は(ハイビジョン編集でもしない限り)自己満足の域に入りつつあると思いますが、でも RAW 現像をまとめてやるときなんかは優位な差が見られるほどにはパフォーマンスアップできたので満足です。CPU 自体にはまだ余力がありそうで、電圧をいじってやればどうやら 4GHz 前後までは狙えるらしいので、常用はしないまでも一度試してみたいと思います。



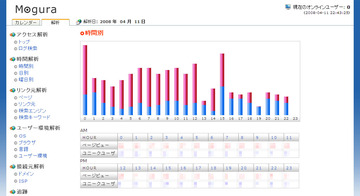
コメント